問診とは、症状を探ることではない。人の声を聴くということ。
『19番目のカルテ 徳重晃の問診』は、ただの医療漫画ではありません。身体の奥底にある“言葉にならない痛み”と、静かに向き合う物語です。
2019年に始まった原作は、専門医の枠からこぼれ落ちた「全体を見る医師=総合診療医」に光を当てました。2025年、TBS日曜劇場での映像化によって、その“問いかける医療”は、さらに多くの人の心へと届き始めています。
この作品に触れたとき、私たちはふと立ち止まるのです。
──「本当に診てもらいたかったのは、体じゃなくて、心だったかもしれない」と。
1. 『19番目のカルテ』の原作者・富士屋カツヒトとは
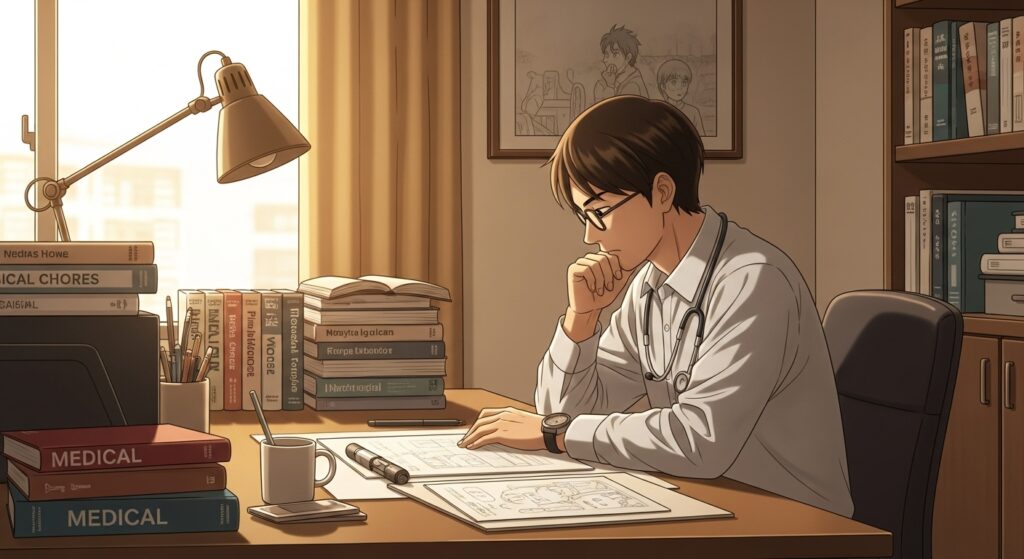
“この物語は、誰かの心に届くために生まれた”。
そう確信させてくれるのが、原作者・富士屋カツヒトの描く世界です。
彼は医師ではありません。けれど、彼の家には医療現場の空気が流れていた。
医療従事者の家族として過ごした日常、その記憶が彼の視線を形づくったのでしょう。
本作では、医療原案として現役の総合診療医・川下剛史が協力。半年以上もカンファレンスに同席し、取材を重ねた富士屋は、「正確な診療プロセス」ではなく、「患者が医師に心を開いていく時間」を丹念にすくい上げていきました。
派手な手術も、天才医師の神業もありません。
ただ、名前を呼び、顔を見て、暮らしを聞き、心の奥に触れる。それが“総合診療”という医療であり、富士屋が描きたかった「19番目の医療」なのです。
2. 富士屋カツヒトが描く医療漫画のリアルさ

『19番目のカルテ』がこれほどまでに心を揺らすのは、単に“病名を明かす物語”ではないからです。
この作品が描くのは、“医師が患者と心を通わせるまでの時間”。
現代の医療現場では、専門性が細分化されすぎて、患者は“どの科に行くべきか”から迷い始めます。けれど、総合診療医・徳重晃は違う。
彼はその迷いごと、丸ごと受け止めるのです。
原作のリアリティは、富士屋カツヒトの徹底した取材姿勢に支えられています。彼は半年以上、総合診療のカンファレンスに参加し、“医療というよりも、人と人との信頼関係”を中心に据えて描いていきました。
例えば、最初に問診をする時、徳重が患者の目をまっすぐ見てこう言います。
「何か変だなって、思うことはありませんでしたか?」
この言葉には、医学的な意図を超えた「その人の内側を尊重する姿勢」があります。
「先生、この人は本当に、私の話を聞いてくれるんだ」──そう思える関係が生まれた瞬間に、初めて“診察”が始まるのです。
この“心を診る医療”こそが、富士屋が漫画というメディアで描きたかった核心。
それは「知識」ではなく「まなざし」の問題であり、そして「治療」ではなく「理解」の物語でした。
3. 原作とドラマの違いを徹底考察

原作が描いた“医療の静けさ”は、映像の中でどのように息づいたのか──。
2025年夏、TBS日曜劇場で『19番目のカルテ』が映像化されました。主演は松本潤さん。静かで理知的、そして温かさをたたえた総合診療医・徳重晃を、静謐な存在感で体現しています。
演出は『コウノドリ』などを手がけた坪井敏雄氏、脚本は坪田文氏。
医療ドラマにありがちな“奇跡”や“スーパードクター”を排除し、原作が持つリアルさと“人間の奥行き”を見事に映像化しました。
印象的だったのは、患者とのやり取りの“間(ま)”をきちんと残した演出です。
対話が止まる沈黙の時間──そこに浮かび上がるのは、言葉にならない痛み。
それを映像で“見せる”勇気に、このドラマの誠実さが宿っていました。
原作者の富士屋カツヒト氏も撮影現場に足を運び、「こういう感じなんだ」と実感を重ねたと言います。
彼が描いた“心の問診”は、演技というフィルターを通しても、濁らず、ぶれず、観る者の奥にまっすぐ届いていきました。
原作とドラマ──どちらも「命を診ること」の本質に迫る物語。
けれど、漫画が“想像させる感情”ならば、ドラマは“共有させる体温”なのかもしれません。
4. 登場人物たちの心理描写から見る医療の“人間味”

『19番目のカルテ』が他の医療ドラマと決定的に異なるのは、「治す」よりも「聴く」ことに焦点を当てている点にあります。
身体の症状を追うだけでは見えてこない“生きづらさ”や“孤独”。
それらを、登場人物の表情や沈黙、ほんのひと言の言葉から、丹念にすくい上げていくのです。
たとえば、全身の痛みを訴える百々(もも)という患者のエピソード。
何度も病院を回っても「異常なし」と診断され続けた彼女に、徳重晃は静かにこう言います。
「あなたの痛みは、ちゃんと本物です」
このひと言が、どれだけ彼女を救ったことでしょうか。
人は、痛みそのものよりも「わかってもらえない痛み」によって深く傷つくのだと──
このシーンは私たちに、そんな医療の根源的な問いを差し出してくるのです。
また、ドラマ版の演出では、徳重と患者が“ただ黙って向き合う”時間がとても印象的です。
その沈黙のなかに、医師の迷いも、患者の葛藤も、確かに息づいている。
医療とは、言葉のキャッチボールではなく、信頼の往復。
それをこの作品は、誰かの人生を語るように、ゆっくりと私たちに教えてくれます。
5. 読者・視聴者の声と評判:共感が広がる理由

『19番目のカルテ』を読んだ人、観た人の多くが、こう口にします。
「気づけば、涙がこぼれていた」
でもその涙は、物語の感動というよりも、自分自身の過去と静かに重なった瞬間のもの。
──「あのとき、私も誰かにちゃんと“聴いて”ほしかった」
──「あの痛みを、わかってもらえるだけで救われる気がした」
読者レビューでは、「総合診療医という存在を初めて知った」という声とともに、「患者の背景にここまで丁寧に寄り添う医師が実在することに驚いた」といった反響も目立ちます。
また、ドラマ放送後のSNS上では──
- 「初回から心をわしづかみにされた。言葉の少なさが、逆に感情を強く揺さぶる」
- 「医者と患者の“信頼の始まり”を、ここまで丁寧に描いたドラマは初めて」
- 「派手な演出がないぶん、日常の中の“しんどさ”が自分ごととして胸に残る」
共感される物語には、共感“されない”日々の痛みが、静かに包み込まれている。
それを読み手に気づかせてくれるのが、この作品の優しさであり、強さなのだと思います。
まとめ:『19番目のカルテ』が今、私たちに問いかけるもの
『19番目のカルテ』は、医療の物語であると同時に、“聴かれなかった感情たち”を拾い上げる物語でもあります。
総合診療医という存在は、症状を探るのではなく、その人自身の暮らしや心の声に目を向ける医師です。
そしてこの物語は、「身体の不調の奥に、どんな孤独が眠っているのか」を、静かに問い続けています。
原作を読むとき、私たちは“あの痛み”を思い出します。
ドラマを観るとき、私たちは“あの沈黙”の意味を考えます。
どちらも、物語の中でありながら、まるで自分自身の記憶を再生しているかのような体験。
だからこそこの作品は、読み終えた後、観終わった後にもずっと残り続けるのです。
──あなたは、最後に誰の声を聴きましたか?
それはきっと、あなた自身の心だったのかもしれません。




コメント