「この歌、なんか朝ドラっぽくない」
『あんぱん』の放送が始まった朝、SNSのタイムラインに流れてきたこの言葉に、私はふと立ち止まりました。
確かに、主題歌「賜物(たまもの)」は、それまでの朝ドラの“肌ざわり”とは少し違う。
やさしく背中を押してくれるような、あるいは季節の手触りを包み込むような、そんな曲たちとは別の位置に立っている。
それは「合わない」のではなく、むしろ“寄り添う距離感”そのものを変えてきたようにも思えたのです。
本記事では、この違和感がなぜ生まれたのかを丁寧にたどりながら、「賜物」という言葉の読み方や、RADWIMPSがこの曲に託した意味、そして『あんぱん』という物語と主題歌のあいだに生まれる「問い」の正体を探っていきます。
それは、ただの分析ではありません。
“朝の10分”を生きる私たち一人ひとりが、この歌に対して抱いた違和感の奥に、何を見出すのか——
そこに、新しい「朝ドラとの向き合い方」が浮かび上がるかもしれません。
【1】「朝ドラらしくない」?——“合わない”という違和感の正体
「賜物」が発表された直後、多くの視聴者が抱いたのは、「歌詞が難しい」「朝にしては重すぎる」という感覚でした。
RADWIMPS特有の詩的で抽象的な表現、厚みのあるサウンド、そして早口でたたみかけるような言葉の連なり。
そのどれもが、戦後という具体的な時代を描く『あんぱん』のリアリズムとは、まるで別の時間軸を生きているように感じられたのです。
たとえば、「うまれてきたことが すでに賜物なんだ」という一節。
それは壮大で、哲学的で、優しい。しかし同時に、日々の暮らしの中で小さな選択を積み重ねていく『あんぱん』の登場人物たちには、あまりに遠い言葉に思えるかもしれません。
この違和感は、単なる感覚的なズレではなく、「語るスピード」と「受けとめるスピード」の食い違いでもあると思います。
朝という時間帯、わたしたちはまだ“完全には起きていない”。
頭と心のあいだに膜があり、情報よりも「空気」や「音色」で物語に触れたいと願っている。
そこに、全力で問いかけてくるような主題歌が現れたとき——“合わない”と感じるのは、むしろ自然な反応なのかもしれません。
けれど、その違和感こそが、今作『あんぱん』の核心なのだとしたら。
この主題歌が、やさしい顔をした朝ドラのふりをして、私たちにそっと手渡そうとしている“問い”だとしたら。
そんな視点から、次は「賜物」という言葉の読み方と、その奥にある意味を見ていきましょう。
【2】「賜物(たまもの)」の読み方と意味——タイトルに込められた意図を読み解く
「賜物」と書いて、「たまもの」と読みます。
この読み方に、どこか懐かしさを感じた方もいるかもしれません。
それは、昔話や宗教的な文脈、あるいは祖父母が口にしていたような言葉の響きをまとっていて、現代のスピード感からは少し外れた、やさしい“間”を持つ言葉です。
「賜物」とは、「神や目上の人から授かったありがたいもの」という意味を持ちます。
命や健康、出会いといった、努力では手に入らない“授かりもの”に対して使われるこの言葉は、どこか慎ましく、けれど深い敬意と感謝の念を含んでいます。
英語で言えば「gift」や「blessing」に近いですが、「賜物」には“自分の意志ではない”という余白があり、そこに日本語独自の受容の美学が宿っているように思います。
『あんぱん』の世界で描かれるのは、敗戦の混乱を経て、新しい命が生まれ、かすかな希望をつなぎながら人々が生きていく姿です。
「うまれてきたことが すでに賜物なんだ」——この歌詞が象徴するのは、「命が与えられたことそのものに意味がある」という祈りのようなメッセージです。
それは、苦しみや矛盾のなかで揺れ動く登場人物たちを、声高ではなく、静かに、けれど確かに包み込む言葉でもあるのです。
また、“たまもの”という音の響きにも注目したいところです。
「ま」の音を中心に据えた三音は、母音が柔らかく、リズムが丸い。
現代語ではなかなか見かけないこの柔らかさが、歌詞全体に温度を与えており、曲の後半で繰り返されるたびに、少しずつ心にしみこんでいきます。
つまり、「賜物」という言葉は、意味としても、響きとしても、“一度では理解しきれないもの”として曲の中央に置かれている。
それこそが、毎朝このドラマに触れる私たちが、時間をかけて問い直していくべき「主題」なのかもしれません。
【3】RADWIMPSの表現と朝ドラの“文法”のすれ違い
RADWIMPSがこの主題歌「賜物」を手がけたと知ったとき、多くの視聴者は「意外だ」と感じたかもしれません。
確かに彼らは、『君の名は。』『天気の子』などで壮大な感情と世界観を音楽で表現する力を持ち、若者たちのリアルとファンタジーのあいだを縦横無尽に行き来する“現代の詩人”でもあります。
一方で、朝ドラという枠組みは、これまで“日常の尊さ”や“庶民の足音”に寄り添ってきた場所でもあります。
短いオープニングのなかに、「ああ、今日もはじまるな」と思わせる余白と親しみが必要とされる——その“朝ドラの文法”において、RADWIMPSの表現は、あまりに鋭く、鋼のように硬質にも感じられるのです。
たとえば、彼らの言葉には、リズムの緻密さと音の密度があります。
「賜物」の冒頭から続く、連続する“助詞を排したフレーズ”の連打は、まるで言葉が感情を追い越していくような加速感を生み出します。
それは思春期の苛立ちや、名前のない感情を抱える若者には刺さる一方、朝の時間帯や多世代の視聴者層にとっては「息をつく間もない」と感じられてしまうのかもしれません。
また、音の構築においても、ストリングスとエレクトロが混ざり合う壮大な編曲は、ある種の“エモーショナルな壁”を作っているように思えます。
この「壁」は、登場人物の息づかいをリアルに感じたい朝ドラファンにとって、時に“距離”として作用してしまうのです。
けれど私は思うのです。
この「合わなさ」や「すれ違い」こそが、今作『あんぱん』にとってはむしろ必要な選択だったのではないか、と。
わかりやすい共感よりも、じわじわとにじんでくる問いの方が、人の心に長く残ることもある。
RADWIMPSというアーティストの“異物感”は、そうした感情の熟成を、無意識のうちに私たちに求めているのかもしれません。
【4】制作サイドが語る「違和感」を選んだ理由
「この主題歌は、あえて“合わなさ”を選んだのではないか」——そんな憶測を裏づけるように、制作陣の言葉には、明確な“挑戦”の意思が刻まれていました。
NHKの公式インタビューによれば、プロデューサーは「一筋縄ではいかないドラマにしたい」と語り、「毎朝、視聴者の受け止め方が少しずつ変わっていくような主題歌を」と、あえて“ストレートではない表現”を求めていたのです。
たとえば、これまでの朝ドラでは、主題歌が“作品の解説”や“感情のガイド”となるケースが多く見られました。
『らんまん』の「愛の花」(あいみょん)や、『おかえりモネ』の「なないろ」(BUMP OF CHICKEN)などは、まさにその代表例です。
いずれも“わかりやすく心に寄り添う”ことを大切にしており、主題歌と物語がまるで双子のように歩調を合わせていました。
けれど『あんぱん』では、その歩調を「少しだけ」ずらした。
言い換えれば、主題歌は“先を歩く問いかけ”であり、視聴者が毎朝の視聴体験を通して、徐々にその意味を咀嚼していく“対話の種”として置かれているのです。
実際、「賜物」は初回からすぐに心にすっと入ってくる曲ではありません。
けれど数日、数週間が経つにつれて、「この曲がないと始まらない」と感じる声も増えてきている。
それはまるで、初めは飲みにくいけれど、じわじわと効いてくる薬のような存在であり、「朝ドラ受け」すら追いつけない速度で、視聴者の感情の奥に入り込んでいくようです。
この選曲は、視聴者との信頼関係があってこそ成立する、大きな冒険だったと言えるでしょう。
「親しみやすさ」を超えて、「今を生きるための物語」として、主題歌が“心の足元”を揺らす——
その余白の設計にこそ、朝ドラ『あんぱん』という作品の本質が宿っているのではないかと思うのです。
【5】“合わない”からこそ響くもの——「賜物」が問いかける希望
私たちはときに、心にしっくりこないものを遠ざけがちです。
けれど、“合わない”と感じるその違和感の奥には、まだ言葉になっていない感情や、気づけていなかった問いが眠っていることがあります。
「賜物」は、まさにそんな“まだ開かれていない扉”を、朝という日常のなかにそっと置いた歌なのだと思います。
この主題歌は、声高に何かを主張するのではなく、ただ静かに「命は授かるものなのだ」と語りかけてきます。
生まれてきたこと、生きていること、それ自体がもう“贈りもの”なのだと。
それは、戦後の混乱を生き抜く主人公たちの人生そのものを象徴する言葉でもあり、同時に、現代のわたしたちにも通じる普遍的な祈りではないでしょうか。
「賜物」という言葉の響きには、どこか過去から届けられた手紙のような温もりがあります。
今はまだピンとこない。だけど、何度も耳にするうちに、ふとした瞬間に涙がこぼれてしまう——そんな“感情の熟成”が、この曲には備わっているのです。
そして、違和感という名の“ズレ”があるからこそ、ドラマの物語と、視聴者の生活のあいだに、もうひとつ別の「余白」が生まれる。
それは、誰かの経験や記憶と、自分自身の感情が交差する“共感の回廊”とも言える場所。
「賜物」は、その入口として、あえて“分かりにくく”あろうとしているのかもしれません。
だから私は、この主題歌を「合わない」と感じた人の心にこそ、いずれ深く届くのではないかと、静かに信じています。
それは、朝ドラが単なる物語以上のものとして、わたしたちの人生にそっと寄り添ってくれる証でもあるのです。
まとめ:「賜物」が私たちに残すもの
『あんぱん』の主題歌「賜物(たまもの)」は、多くの人が「なんとなく合わない」と感じる曲かもしれません。
けれどその違和感は、作品の失敗ではなく、むしろ「問い」として私たちに差し出されたものなのだと思います。
音楽が物語に寄り添いすぎるとき、感情はスムーズに動きます。
でも、ときに“寄り添いきらない音楽”が、視聴者の心に別の感情の波を起こしてくれることもある。
「賜物」は、そんな新しい可能性を示す、挑戦的な主題歌でした。
“合わない”から始まった違和感は、もしかすると「今まで見てこなかった感情に目を向けてみて」という呼びかけなのかもしれません。
そのズレの中で、私たちは少しだけ立ち止まり、自分の命や家族、大切な人との関係を見つめ直すのです。
『あんぱん』という物語とともに、「賜物」という言葉の重みを、何度も何度も受け取り直す——
その過程自体が、朝ドラを“見る”という体験を、“生きる”という営みに近づけてくれているのではないでしょうか。
違和感の先にこそ、共鳴は生まれる。
この歌が、あなたにとって、今日の朝を少しだけやさしくする“たまもの”でありますように。


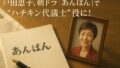

コメント