なぜ今、“児童相談所”のドラマが月9に必要なのか
「誰かを守りたい」と願うとき、私たちは本当は、自分の中の“救えなかった何か”と向き合っているのかもしれません。
2025年7月、フジテレビ月9枠で放送されるドラマ『明日はもっと、いい日になる』。舞台は児童相談所。主人公は、刑事から異動してきた若き児童福祉司・夏井翼(福原遥)。彼女が出会うのは、言葉にできない痛みを抱えた子どもたちと、傷を隠したまま懸命に生きる大人たちです。
今、この社会において、“声にならない声”に耳を澄ませることの意味とは何か――。本作は、そんな問いを静かに投げかけてきます。ヒューマンドラマとしての芯を持ちながら、正義でも理想でもなく、「人が人であること」のリアリズムを描こうとする作品です。
この記事では、あらすじやキャストはもちろん、脚本家・谷碧仁の筆がどのように感情を言葉にしているのか、主題歌「小さな歌」に込められた余韻、そして“このドラマでなければならない理由”まで、ひとつひとつ丁寧にひもといていきます。
これはきっと、「過去の自分」ともう一度出会うためのドラマ。読者のあなたが、物語の中に“自分の記憶”を見つけられるように、そんな視点で書き進めてまいります。
あらすじ|心の声を聞き取る場所で、もう一度「生き方」と出会う

神奈川県警の刑事・夏井翼(福原遥)は、職務中のある出来事をきっかけに、児童相談所への異動を命じられる。
それは現場では「左遷」と囁かれるような異動だったが、翼自身もまた、捜査の現場で何かを失いかけていた。
新たな勤務地は、海辺に佇む児童相談所。そこでは、日々「誰にも気づかれなかった小さな命」が運ばれてくる。
家庭内暴力、育児放棄、ネグレクト、孤独――ここに来る子どもたちは、叫ぶことすらできないまま、沈黙の中で助けを求めていた。
翼は、ベテラン福祉司・蔵田総介(林遣都)、児童心理司・蒔田向日葵(生田絵梨花)、そして同僚たちと共に、
「声なき声」に耳を澄ませる日々を送ることになる。だが、過去に心を閉ざしたままの翼は、他人の痛みに正面から向き合うことに戸惑いを隠せない。
一方、児童相談所のチームには、それぞれに“理由”を抱えてここにいる者たちがいた。
福祉を選んだ背景には、傷、後悔、そしてどこかで誰かを救えなかった記憶がある。翼もまた、“誰かを守りたかったあの日の自分”に立ち返ることになる。
これは、子どもたちを守る物語でありながら、大人たち自身が「守れなかった自分」と向き合う物語でもある。
「救う」とは、「寄り添う」とは何か。答えのない現場で、それでも希望の種を手渡し続ける人々の、
静かな戦いと、再生の物語が今、幕を開ける。
キャスト紹介|福原遥・林遣都・生田絵梨花ら、繊細な人間を演じる名優たち

『明日はもっと、いい日になる』が胸を打つ理由のひとつは、「ただの登場人物」ではなく、「そこに生きている人間」として描かれるキャスト陣の表現力にあります。
主人公・夏井翼を演じるのは、福原遥。
これまでの“透明感”というイメージを脱ぎ捨て、不器用で、傷つきやすく、それでも立ち止まらない“強さと脆さが共存する女性像”を体現しています。
ときに感情を抑え込み、ときに抑えきれずこぼれる涙――そのリアルさが、観る者の記憶を揺さぶります。
翼のバディとして描かれるのは、林遣都演じるベテラン福祉司・蔵田総介。
理屈ではなく「経験」と「まなざし」で子どもと向き合う彼の姿は、“寄り添う”とはどういうことかを教えてくれる存在です。林の静かな芝居には、言葉にならない重みがあります。
児童心理司・蒔田向日葵役に生田絵梨花。
柔らかな雰囲気の奥に、強い信念と過去の痛みを抱えた複雑な人物像。彼女の眼差しがふと鋭さを帯びるとき、
“この人もまた、誰かを救えなかった記憶を持つのだろう”と観る者に語りかけてきます。
さらに、風間俊介、小林きな子、勝村政信、柳葉敏郎といった実力派が揃い、
職業ドラマとしての厚みだけでなく、「生き方の多様性」を登場人物それぞれに宿らせています。
このドラマのキャスティングは、「正しさ」を演じる人ではなく、「葛藤」を抱えた人たちで構成されています。
だからこそ、私たちは彼らに感情を重ねることができる。彼らの迷いや躊躇が、私たちの記憶と響き合う――それがこの作品の強さです。
子役たちの存在が物語を動かす|吉田萌果・二ノ宮陸登ほか注目の若き才能

このドラマを「心に残る物語」にしている最大の理由――それは、子役たちの“声なき演技”にあります。
岩本花蓮役の吉田萌果、野口風雅役の二ノ宮陸登、坂西青葉役の市野叶など、名の知れた俳優ではない子どもたちが、それぞれの役として“そこにいる”だけで、観る者の心に深く刺さるのです。
彼らの演技は、セリフではなく、「目線」や「沈黙」で語られます。
殴られることに慣れてしまったような無表情、優しさに触れたときにだけ浮かぶ戸惑い――
そうした表情の一瞬一瞬が、ドラマ全体の重力を引き上げているのです。
彼らはただの“事件の被害者”として描かれているのではありません。
それぞれに物語があり、それぞれが人生の「どこかで切り取られた時間」を抱えている。
そして、傷ついているのは彼らだけでなく、彼らと関わる大人たちもまた“過去に置き去りにした自分”と向き合わされるのです。
福原遥演じる翼は、子どもたちの存在によって自らの記憶を掘り起こされていく。
林遣都、生田絵梨花らもまた、「どうしてこの仕事を続けているのか」という問いに直面します。
この作品において、子どもたちは“救われる存在”ではなく、“大人たちを変える存在”でもある。
その対等性こそが、本作を「社会派ヒューマンドラマ」ではなく、「人間の再生の物語」へと押し上げているのです。
脚本・谷碧仁とは誰か|“舞台的リアリズム”がドラマに与える力
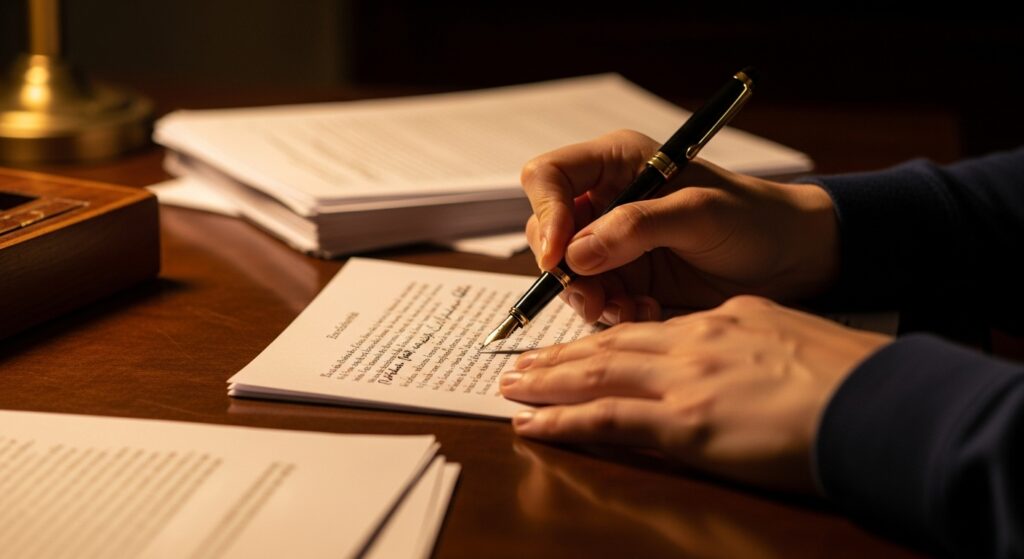
『明日はもっと、いい日になる』は原作のない完全オリジナル作品。その言葉をゼロから紡ぎ出したのが、劇作家・脚本家の谷碧仁(たに・あおと)です。
谷は劇団「時間制作」の主宰として、人間の本音と葛藤を、“台詞ではなく、沈黙や行間”で描くことに長けた作家です。
舞台を中心に活動してきた彼にとって、物語とは「語られるもの」ではなく、「滲み出すもの」。それが、本作の静かな強度につながっています。
ドラマでは、社会的に語られにくい“福祉の現場”を扱いながらも、押しつけがましい正義感や道徳観は排除されています。
かわりにあるのは、「答えの出ない問い」に向き合う人たちの揺れ。子どもを救いたいと思いながら、うまく距離を取れずに苦しむ大人たちの姿が、とてもリアルに描かれています。
谷自身はインタビューでこう語っています。
「誰かを助けようとするとき、同時に自分の中の“誰かを見捨てた記憶”と向き合うことになる」
その言葉通り、本作は“救うことの正しさ”ではなく、“救えなかった記憶を背負いながら生きていくことの誠実さ”を描いています。
それは、まさに谷碧仁という作家がずっと描いてきたテーマの延長線上にある物語。
だからこのドラマは、ただのテレビドラマではなく、「生き方の再演出」なのです。
登場人物たちは、私たちと同じように、迷い、ためらい、それでも誰かと向き合おうとする。
谷の脚本は、その過程を決して焦らせず、そっと伴走するように進んでいきます。
ロケ地巡礼|逗子・横須賀・横浜…風景が語る“心の再生”

このドラマのもう一人の登場人物――それは、“風景”です。
物語の中心となる児童相談所は、神奈川県・逗子海岸沿いに実在する建物をロケ地に使用して撮影されています。
エピソードの多くが、潮の香りが漂う海辺の街を背景に進行し、視聴者の心に「開かれた空間」と「閉じられた心」のコントラストを強く残します。
その他、横須賀市・観音崎自然博物館では外観シーンが撮影され、横浜市青葉区のアパート、浦和美園駅、茨城県つくば市など、多様な地域が“心の移動”を映像として支えています。
児童相談所という“社会的に閉じた空間”を描きながら、常に海の存在が映し出されるのは偶然ではありません。
海はときに穏やかで、ときに荒れる。満ち引きのある自然のリズムは、人の心の不安定さと重なり、それでもどこか「循環する希望」を示してくれる存在です。
あるシーンでは、翼が心を閉ざした子どもとただ無言で海を見つめる場面があります。
言葉は交わされない。けれど、その場面には何かが“届いている”と感じさせる説得力がありました。
ロケ地の選定は、このドラマが描く「再生」や「希望」を風景で支える演出の一環。
訪れた人が、ただの撮影地としてではなく、「感情の記憶を辿る場所」として風景と再会できる、そんな深さが宿っているのです。
主題歌「小さな歌」JUJUの声に込められた「優しさの記憶」

物語の幕が下りる瞬間、エンドロールと共に流れ出す音楽。それは、1時間の感情の波をそっと包み込む“もうひとつの物語”です。
『明日はもっと、いい日になる』の主題歌は、JUJUの「小さな歌」。
この曲は、派手なサビや盛り上がりはありません。むしろ、静かに、寄り添うように始まり、最後まで大声にならない。
それはまるで、翼たちが子どもたちに接するときの距離感のようです。
JUJUの歌声は、哀しみを肯定するようなやわらかさを持ち、「それでも、明日は来るよ」と微かに背中を押してくれる。
特に印象的なのは、「あなたの声が届いたとき、やっと私は私を赦せた」という一節。
これは、ドラマの本質と完璧に呼応しています。
なぜなら、この物語に登場する誰もが、「誰かの声に出会うことで、かつての自分と和解していく」からです。
子どもが大人を変え、大人が子どもに学び直す――その循環のなかで紡がれる“心の再生”に、この歌はそっと寄り添います。
主題歌とは、物語の最後にもう一度心を見つめ直す“鏡”。
JUJUの「小さな歌」は、まさにその役割を果たし、視聴者の胸に「まだ名前のついていない感情」を残してくれます。
制作陣の言葉から読み解く、このドラマの“本当の狙い”

『明日はもっと、いい日になる』は、ただ感動を届けるための“お涙頂戴ドラマ”ではありません。
この作品の根底には、「福祉」「命」「対話」――そして「過去と向き合う」という、社会と個人をつなぐテーマが流れています。
脚本家・谷碧仁は、制作発表時にこう語っています。
「誰かを助けるとき、実はその“誰か”に、自分自身が救われていた。
このドラマは、その“交差点”を描きたかったんです」
また、主演の福原遥も、台本を読んだときの第一声でこう漏らしたといいます。
「静かに涙が出そうになりました。
ただ優しいだけじゃない、苦しさも抱えている物語だと感じました」
演出を担当する相沢秀幸は、子どもたちの表情の「一瞬のゆらぎ」にこだわったと語り、
「伝えようとする演技よりも、伝わってしまう瞬間を撮りたかった」と演出意図を明かしています。
このように、制作陣それぞれが、「声に出せない感情」とどう向き合うかをテーマに掲げていることがわかります。
このドラマの“狙い”は、共感ではなく共鳴。
視聴者が自分の過去や誰かとの記憶をそっと思い出す“きっかけ”を届けること。
それがこの作品が目指す“感情の通訳”であり、“心の再生の物語”なのです。
まとめ|「明日はもっと、いい日になる」が私たちに届く理由
物語を見終えたとき、心に何かが残る。それは感動というよりも、「言葉にならなかった想い」がそっと輪郭を持ちはじめるような感覚かもしれません。
『明日はもっと、いい日になる』は、誰かを変える物語ではなく、誰かの存在によって“自分が変わっていく物語”です。
児童相談所という舞台、沈黙を抱えた子どもたち、心に傷を持つ大人たち。
誰もが完璧ではなく、誰もが不完全なまま、それでも「目の前の誰かと向き合おう」とするその姿に、
私たちは、自分自身の「過去」と「明日」の両方を見つけ出すのです。
「明日はもっと、いい日になる」――この言葉は、未来を保証する魔法のようでいて、実はもっと現実的な祈りです。
それは、「今日を少しでもまっすぐに生きた人」だけが、そっと抱ける予感のようなもの。
このドラマは、その“予感”を静かに私たちの心に宿してくれます。
涙の理由がわからなかった夜に。
このドラマは、あなたの心の奥に沈んでいた“まだ名前のない感情”に、やさしい光をあててくれるはずです。




コメント