「お母さん、なんで恋人が3人もいるの?」
そんな言葉を、千夏は心の中で何度も反芻していた。
でも、口にはしなかった。
『彼女がそれも愛と呼ぶなら』は、“普通”を知らずに育った少女が、自分の「違和感」と向き合っていく物語です。
Z世代にとって、「多様性」はもう前提で、「理解できないもの」も無理に否定しない。でも、だからこそ、自分が感じた違和感を“なかったこと”にしてしまいがち。
この物語の主人公・千夏は、そんな時代を生きる私たちに、静かに語りかけます。
「あなたが感じたその“引っかかり”、本当はすごく大事なものかもしれないよ」と。
『彼女がそれも愛と呼ぶなら』とは?
小説とドラマ、二つの形で描かれる“愛の多様性”
『彼女がそれも愛と呼ぶなら』は、一木けいによる同名小説を原作とした、2025年春放送のテレビドラマです。
主演は栗山千明。3人の恋人と共に暮らすシングルマザー・伊麻を軸に、「家族」や「愛」の形を描き出します。
この作品が特異なのは、「複数恋愛=タブー」ではなく、「選択肢のひとつ」として丁寧に描かれていること。
そのうえで、「それを“普通”と信じて育った子どもは、何を感じるのか?」という、今まで語られてこなかった視点——それが娘・千夏なのです。
一木けいの原作が提示する「家族のかたち」
原作小説は2024年刊行。高校生の千夏の目線で、母・伊麻の恋愛と、彼女自身の初恋が交錯していく様子が描かれます。
千夏にとって“家族”とは、母とその恋人たちとの生活。でも、それを誰かに説明することは、できなかった。
その「言えなさ」や「引っかかり」を、彼女は飲み込む。
物語は、そんな千夏がクラスメイトの男子に恋をしていく過程で、自分の中の“常識”と“違和感”に向き合い始める——という流れ。
まるで、何も感じていないふりをしてきた心の蓋が、ゆっくりと開いていくように。
千夏という少女が抱える“違和感”とは
母親の恋愛を見つめる、静かな観察者としての千夏
千夏は、感情を大きくぶつけるタイプではありません。
むしろ、常に一歩引いて、物事を静かに見つめるタイプ。
母・伊麻とその恋人たちのやりとりを見ていても、怒りや拒絶を表に出すことはない。
でも、それは“納得している”という意味ではないのです。
むしろ、あまりに奇妙なものを見続けているうちに、「これは変だ」と感じる力が鈍っていくような、そんな感覚。
「お母さんは、誰が一番好きなの?」
「どうして、同時に3人の人と付き合えるの?」
その問いは、心の奥にずっとある。でも、それを言葉にする勇気が、なかった。
自分の初恋が、常識とぶつかった瞬間
そんな千夏にも、ある日、初めて「恋」と思える感情が訪れます。
相手は、クラスで明るくて人気のある男子。
彼と過ごす中で、千夏は“普通の恋”がどういうものかを、初めて知ることになります。
「独占欲」や「嫉妬」があるのが当たり前。
「好きなら、自分だけを見てほしい」と思うのが、当たり前。
でも、千夏の中には、それに対する違和感も同時に芽生えてしまう。
「お母さんは、そうじゃなかったのに」と。
それは、“普通”を知ったことによって初めて、彼女の中で“家族の特殊性”が浮かび上がった瞬間でもあります。
なぜZ世代に千夏の視点が刺さるのか
「正しさより、リアル」な感情に共感が集まる理由
Z世代は、「多様性」や「理解しあうこと」を重視する一方で、
その“わかってる風”な空気に少し疲れている部分もある。
だからこそ、千夏のように「納得できないけど、受け入れるしかない」と葛藤する姿に、共感する人が多いのです。
彼女の感情は、わかりやすい正解を提示しない。
ただ、“モヤモヤ”をそのまま描く。
そして、その「モヤモヤを認める強さ」が、同じ時代を生きる若者たちの心に刺さるのです。
“多様性”が当たり前になったからこそ揺らぐアイデンティティ
今やSNSでは「恋愛の形に正解はない」「人それぞれでいい」と言われる時代。
でも、「じゃあ自分は何が心地よいのか?」と問われると、立ち尽くしてしまう。
千夏の葛藤はまさにそこにあります。
「多様性」を尊重する自分と、モヤっとしてしまう本音の自分。
そのどちらも否定せず、向き合おうとする千夏の在り方は、多くの若者の「感情のリアル」に近いのです。
「正しさ」より、「本音」。
千夏の視点は、Z世代の“ほんとうの気持ち”をすくい上げてくれる鏡のような存在です。
印象的なセリフとシーンで読む“共感”の理由
「好き、って思ったら、全部許さなきゃいけないの?」
このセリフは、千夏が恋人からの過剰な愛情表現に息苦しさを覚え、ふと漏らした一言です。
相手に好かれることが、なぜか「我慢」や「迎合」に繋がってしまう。
Z世代の恋愛にありがちな“重たさ”や“期待への応え疲れ”を、この一言が鮮やかに言語化してくれます。
「好き」と言われたら、嬉しい反面、何かを差し出さなきゃいけない気がする。
そんな矛盾した感情を抱えた経験がある人なら、きっとこのセリフに「それな…」と頷かずにはいられないはずです。
SNSでバズった共感コメントまとめ
放送後、X(旧Twitter)やTikTokでは千夏のセリフや行動に共感の声が殺到。
特に「なんとなく不快なのに、理由を言葉にできない」場面での彼女の表情や間が、「わかりすぎる」と話題になりました。
「千夏の気持ち、昔の私すぎて泣いた」
「“愛されてるのに苦しい”って、ほんとにあるんだよね」
「この作品、全部“わかってるフリ”してきた自分への手紙みたいだった」
ただの恋愛ドラマではない。
“感情の違和感”に名前をつけてくれる物語として、多くの視聴者の心に残ったのです。
まとめ|“違和感を抱ける感性”こそ、今いちばん大切にしたい
『彼女がそれも愛と呼ぶなら』という物語は、「多様性を理解しなきゃ」「愛を受け入れなきゃ」と、
“優等生”な振る舞いをしてきた私たちに、そっと問いかけます。
「あなた、本当はどう思ってるの?」
「誰かの幸せを祝う前に、自分の気持ち、置いてけぼりにしてない?」
千夏が教えてくれたのは、“違和感を抱ける感性”を大事にすること。
それは、誰かを否定することじゃなく、自分に正直であること。
時代がどれだけ進んでも、「自分が何を心地よいと感じるか」を忘れてはいけない。
この作品は、そのシンプルだけど難しい問いに、もう一度立ち戻らせてくれる——そんな“感情のリマインダー”なのかもしれません。


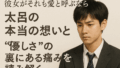
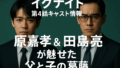
コメント